こんにちは!ギバシです!
いつもブログを見てくださりありがとうございます!

「ギバシさん!作業療法士になったのはいいけど、正直どこから勉強すればいいかわかりません…。先輩たちはみんな忙しそうだし、焦ります…。」
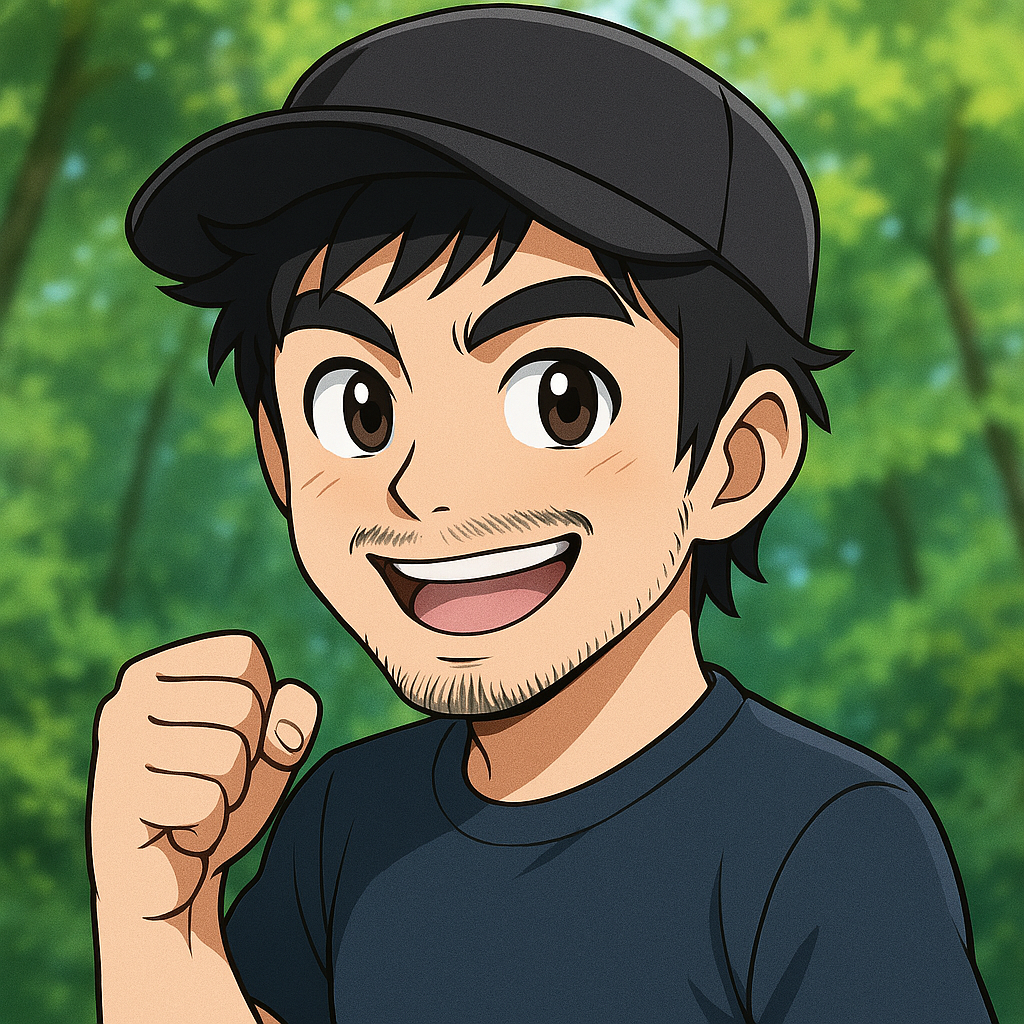
「うんうん、その気持ちすごくわかるよ!俺も新人のときは“とりあえず目の前の患者さんをなんとかする”ので精一杯だったよ。」

「やっぱり最初ってそうなんですね…。疾患も多いし、作業療法ってどんな勉強から手をつけたらいいのか…。」
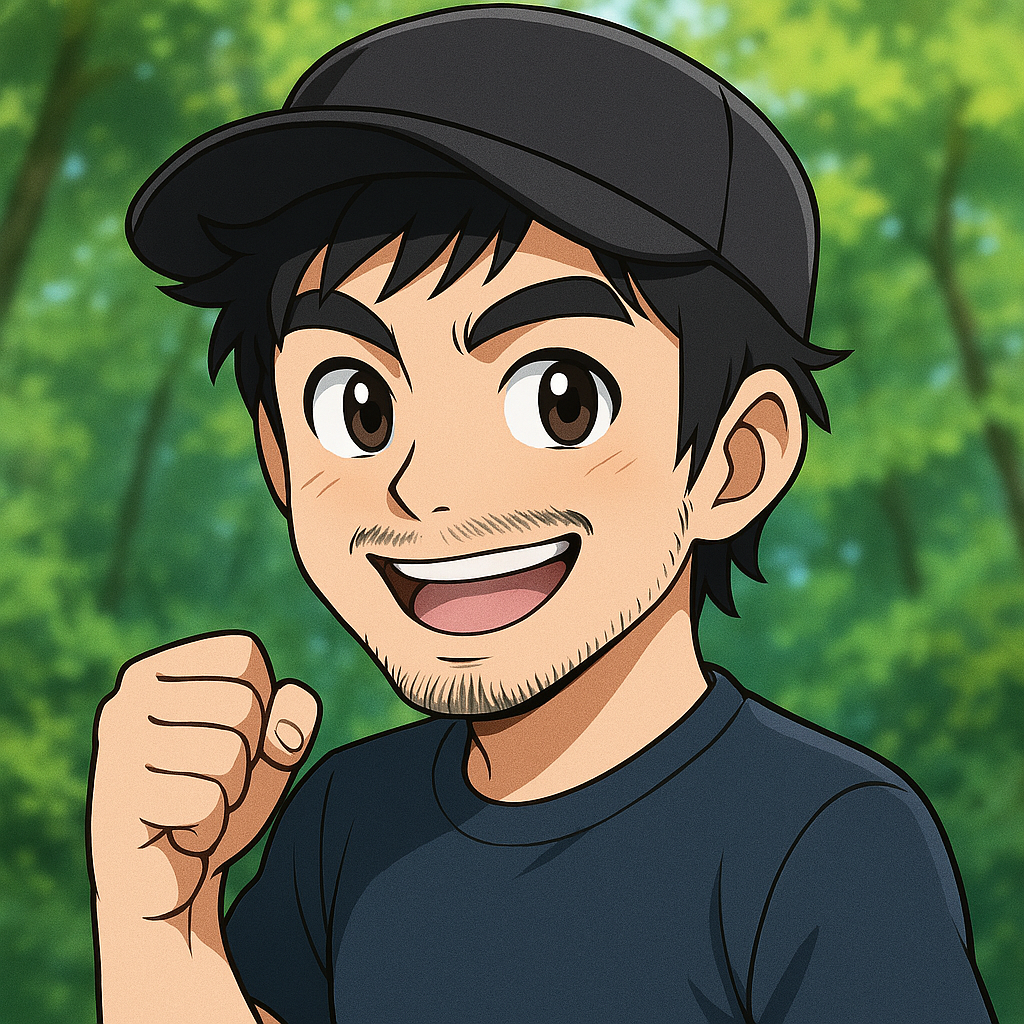
「そうだね。でも安心して!14年現場でやってきた経験から、“まず何を勉強すれば臨床で迷わず動けるか”っていう軸は見えてきたんだ。今日はその話をしようと思う。」

「ぜひお願いします!!」
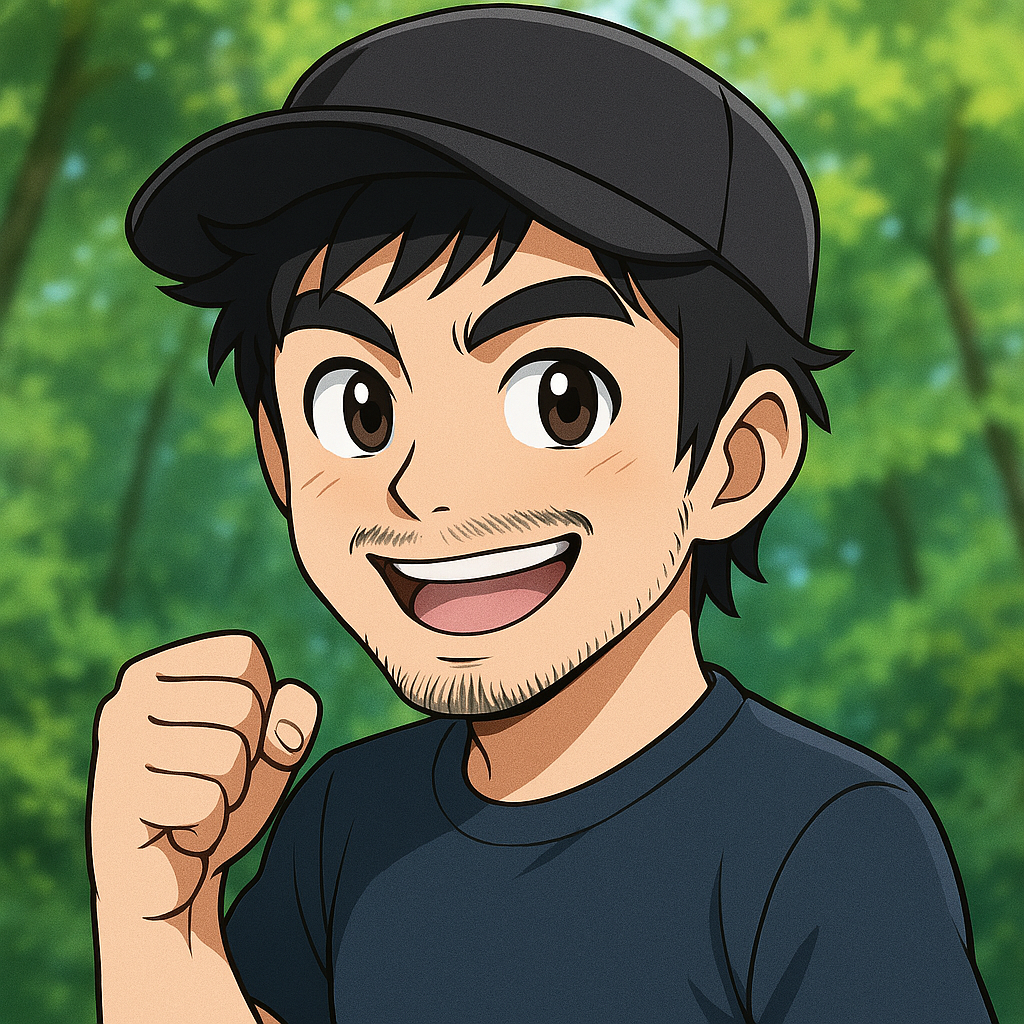
「OK!じゃあ今回は“作業療法士がまず勉強すべき内容”について話していくよ!」
結論:まず、疾患の勉強と作業療法の勉強をせよ!
作業療法士になったら、まず 「疾患の勉強」と「作業療法そのものの勉強」 が大切です。
学校でも学びますが、実際の臨床現場では教科書では拾えない現実がたくさんあります。
順に詳しく見ていきましょう。
疾患の勉強をしよう
疾患を理解することは、評価・治療の土台です。
>疾患を知らないままリハビリを行うと、次のようなリスクがあります。
-
患者さんの状態変化に気づけない
-
病態を見誤り、誤ったアプローチをしてしまう
-
患者さんとの信頼関係が築きにくい
逆に、疾患を理解していると
「この人は今どんな不安を抱えているか」「どんな生活を送ってきたのか」が見えてきます。
つまり、疾患を知ることで“人”をより深く理解できるようになります。
勉強のコツ
-
まずは自分の職場でよく見る疾患から!
例:回復期なら脳卒中、整形外科なら大腿骨骨折など -
評価方法を関連づけて覚える
画像所見・血液検査・注意事項などを、担当患者さんに当てはめながら勉強 -
調べた内容はノートに“患者さん別まとめ”で記録
→ 臨床とリンクしやすく、理解が深まります。
📚 おすすめ本
「病気がみえる」シリーズ図が多く、ビジュアルで理解しやすいので新人にもぴったりです!
作業療法の勉強をしよう
臨床ではよく「理学療法との違い」に悩まされます。
患者さんからすると“リハビリ=全部同じ”に見えることが多いからです。
たとえば、
-
「歩く練習をしてほしい」
-
「マッサージしてほしい」
-
「お手玉や輪投げは幼稚に見える」
なんて言われたこと、ありませんか?
だからこそ、まずは
「作業療法とは何か」を自分の言葉で説明できるようにすることが大事です。
そして、理論に基づいた考え方を持つことが信頼につながります。
💡 学ぶべきポイント
-
作業療法の目的と価値
-
作業の意味(Doing/Being/Becomingの視点)
-
作業療法の理論(MOHO、PEO、認知療法理論など)
特に僕自身は認知療法理論を実践に活かしています。
患者さんの思考パターンを理解することで、リハビリや日常生活支援に深みが出ます。
(この理論については、また別の記事で詳しく解説します!)
📚 おすすめ本
「作業療法士が“作業”を説明できる本」患者さんにOTの意義を伝える力を身につけたい人におすすめです。
🧾 まとめ
作業療法士がまず勉強すべき内容とは?
| 学ぶ内容 | ポイント |
|---|---|
| 疾患の勉強 | 評価・治療の基礎。リスク回避・信頼構築にも直結。 |
| 作業療法の勉強 | OTとしての専門性を説明できるようにする。理論理解が鍵。 |
✍️ ギバシからひとこと
新人のときは「全部勉強しないと!」と思いがちだけど、
“今の自分が関わる患者さん”を中心に学ぶことが一番の近道です。
次回は「作業療法士が考える仕事術シリーズ」をお届けします!
もし知りたいテーマや疑問があれば、コメントで教えてくださいね!
ではまた!
みなさんにとって明日がいい日でありますように!
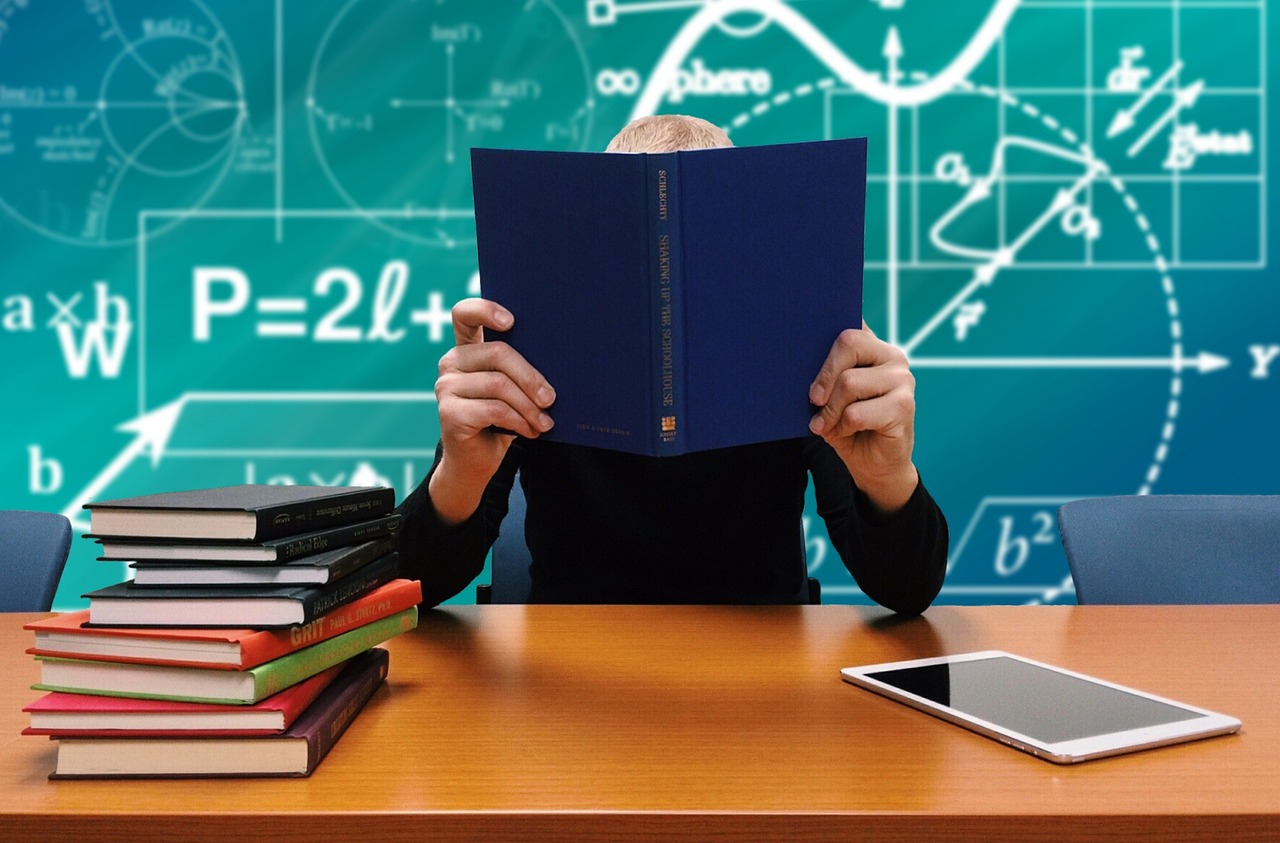


コメント