こんにちは!ギバシです!
いつもブログを見てくださってありがとうございます😊
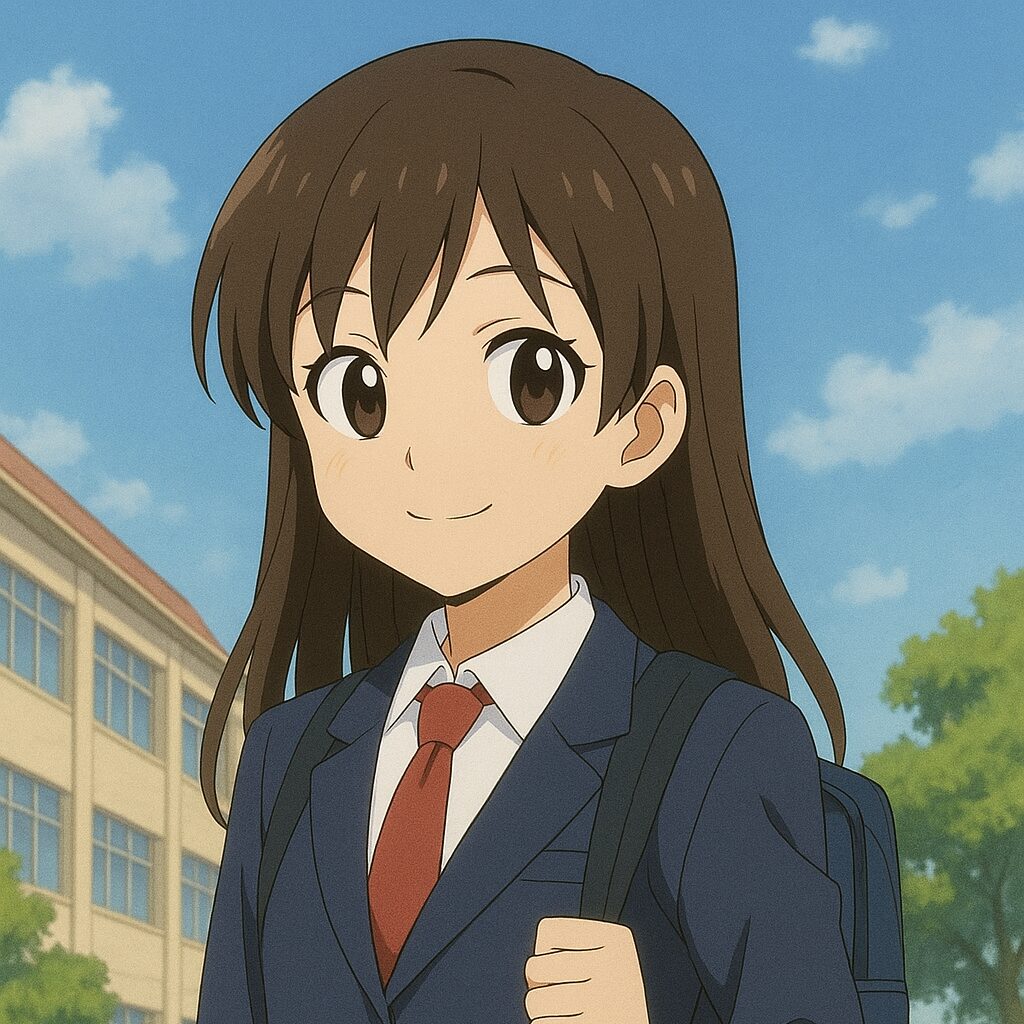
「ギバシさん、この患者さん、どこまで回復できそうかってどう考えればいいんですか?」
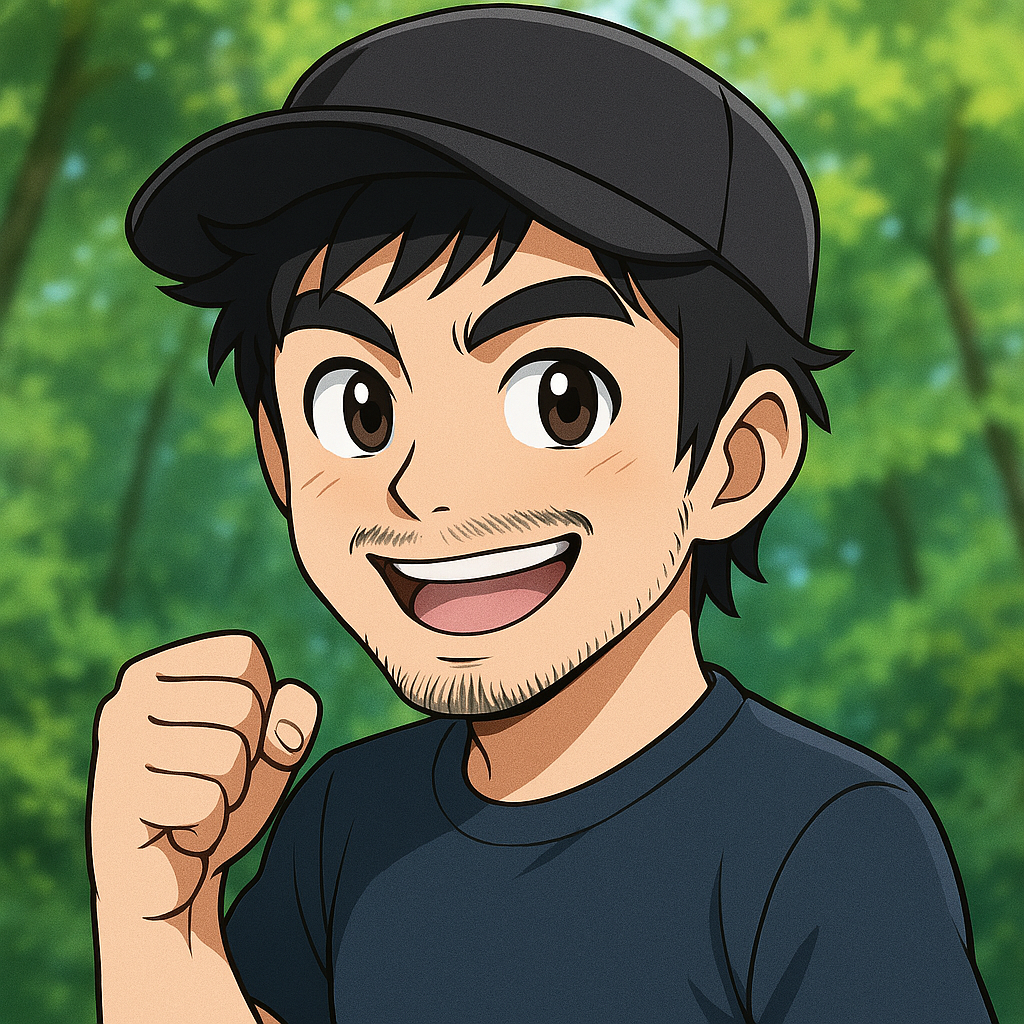
「おっ、いい質問だね!予後予測って、実は“勘”だけじゃなくて理論と根拠が大事なんだよ。」
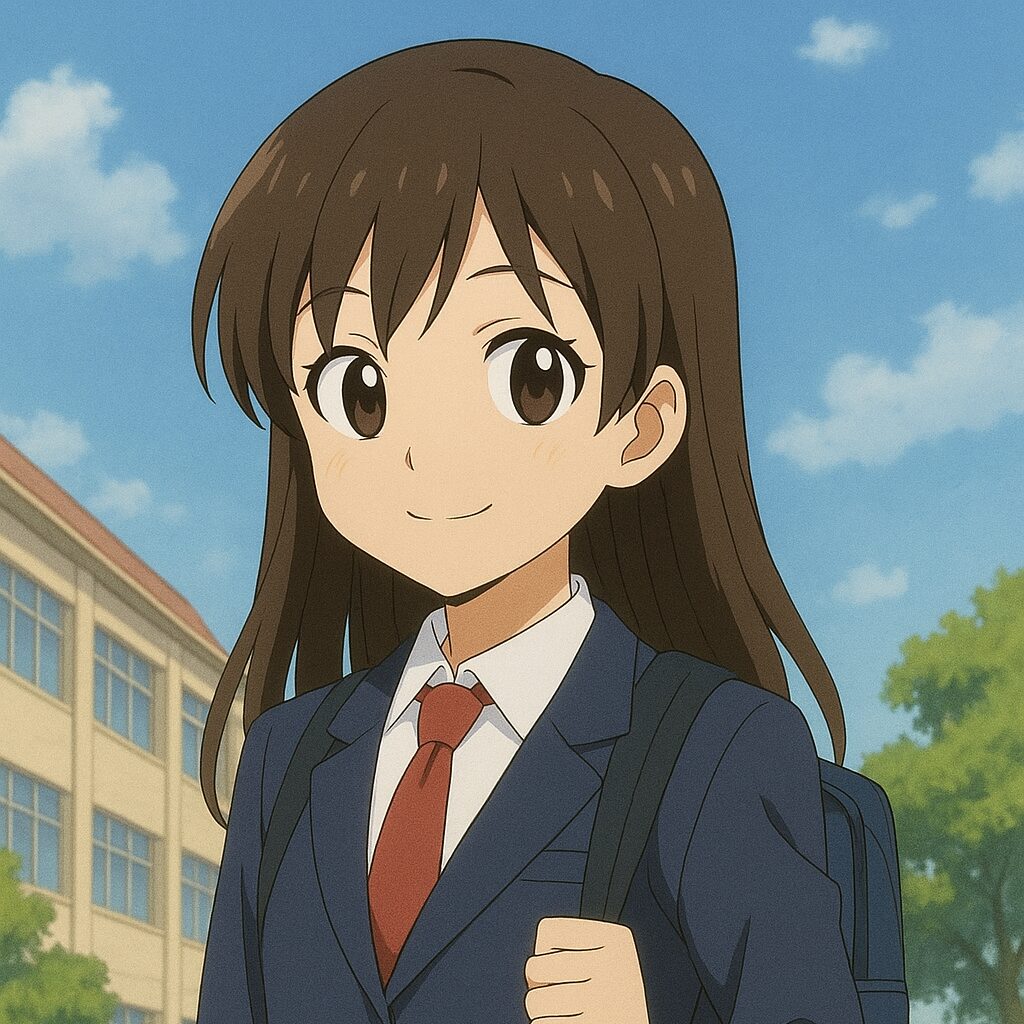
「理論と根拠…?でも、難しそう。」
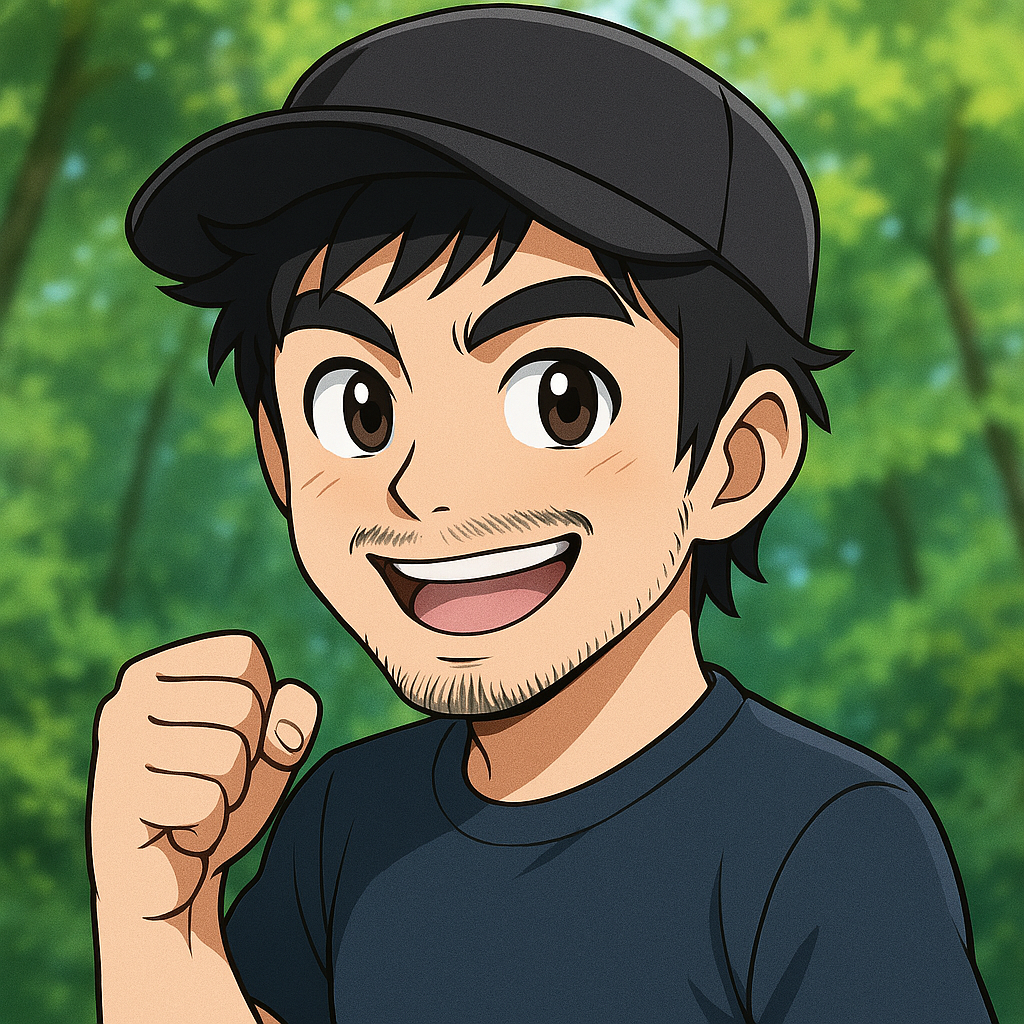
「そんな君にオススメの本があるよ。竹林先生が編集した“臨床5年目までに知っておきたい 予後予測の考え方”って本なんだ。」
📘本の概要
この本は、急性期・回復期・維持期リハビリで働くセラピストが
「患者さんの今後をどう見立て、どう関わるか」を体系的に学べる一冊です。
予後予測と聞くと少し難しそうに感じますが、
著者は実際の臨床現場での判断プロセスを、わかりやすく・具体的に説明してくれています。
そのため、単なる理論書ではなく「明日から実践で使える」構成になっています。
特に急性期や回復期で働くリハビリスタッフは、
患者様の今後の方向性(在宅復帰・施設調整など)を判断する場面が多く、
予後予測は必須の知識・技術になります。
🧠本書のポイント
① 予後を考える3つの軸
- 疾患特性
- 年齢や既往などの個人要因
- 環境・支援体制
この3つの視点を整理して考えることで、
「なんとなくの経験則」ではなく、再現性のある予測ができるようになります。
たとえば同じ脳卒中でも、既往歴や家族支援の有無で回復経過が全く変わる——
そうした“個別性のある予後予測”の視点を丁寧に解説しています。
② 時間経過で見る回復曲線
発症からどの時期にどれくらいの機能回復が期待できるのか、
エビデンスをもとにした回復曲線がとても見やすくまとめられています。
特に「脳卒中」「骨折」「廃用症候群」など代表的な疾患別の回復スピードは、
新人〜中堅スタッフがゴール設定を考えるうえで非常に参考になります。
また、「上肢機能」「歩行機能」「ADL」など、
予後予測に必要なアウトカム評価の種類や使い方も整理されており、
「どの評価を取れば根拠になるのか」が一目で分かる構成です。
③ 多職種連携の中での予後共有
本書が素晴らしいのは、身体機能だけでなく認知面・高次脳機能面の予後も扱っている点です。
脳画像や生理学的指標を用いた予測法も紹介されており、
医師・看護師・ソーシャルワーカーとの情報共有にもそのまま活かせます。
また、「予後をどう伝えるか」というコミュニケーションスキルにも触れており、
若手セラピストが患者や家族に説明する際のヒントが満載です。
🏥臨床での活かし方
自分自身、以前は予後予測を曖昧にしていた時期がありました。
「リハビリのゴール設定」がぼんやりしていて、
医師や家族から質問を受けても、**“経験的な感覚”**で答えてしまうことが多かったんです。
しかしこの本を読んでからは、
「どこまで」「どのくらいの期間で」回復できそうかを具体的な言葉で説明できるようになりました。
たとえば、脳卒中患者様の例では——
「FIMの伸び率」や「初期歩行距離」といった客観的データをもとに、
「この方はあと2週間で〇〇の動作が自立する可能性が高いです」「退院時期はおそらく〇月中旬頃が目安です」
と、チーム全体で共有できるようになったのです。
また、患者様本人との目標設定にも大きな変化がありました。
「なんとなく頑張りましょう」ではなく、
“目に見える合意目標”を立てることで、モチベーションの向上にもつながりました。
結果的に、チーム全体の方向性が一つにまとまりやすくなったと感じています。
📝まとめ
『臨床5年目までに知っておきたい 予後予測の考え方』はこんな方にオススメ!
予後を「感覚」から「根拠」に変えることで、臨床の見え方がガラッと変わります。
この本を読むことで、自分のリハビリの“根拠づけ”が明確になり、
日々の臨床がより楽しく、より自信をもって行えるようになるはずです。
以上、参考になりましたでしょうか?
また次回のブログも楽しみにしてくださいね!
ではまた!
皆様にとって明日がいい日でありますように🌱



コメント